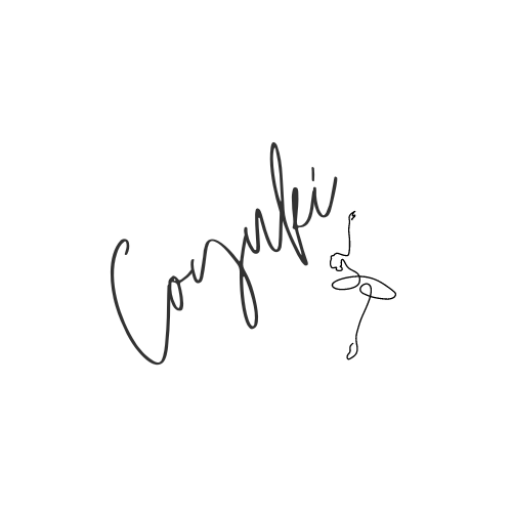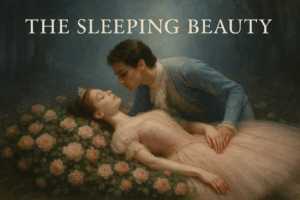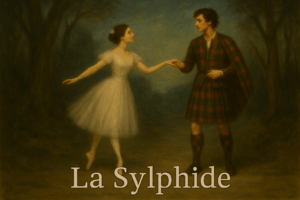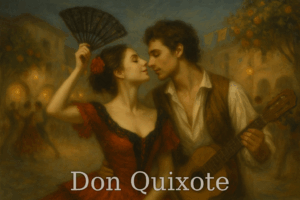※ 当サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。
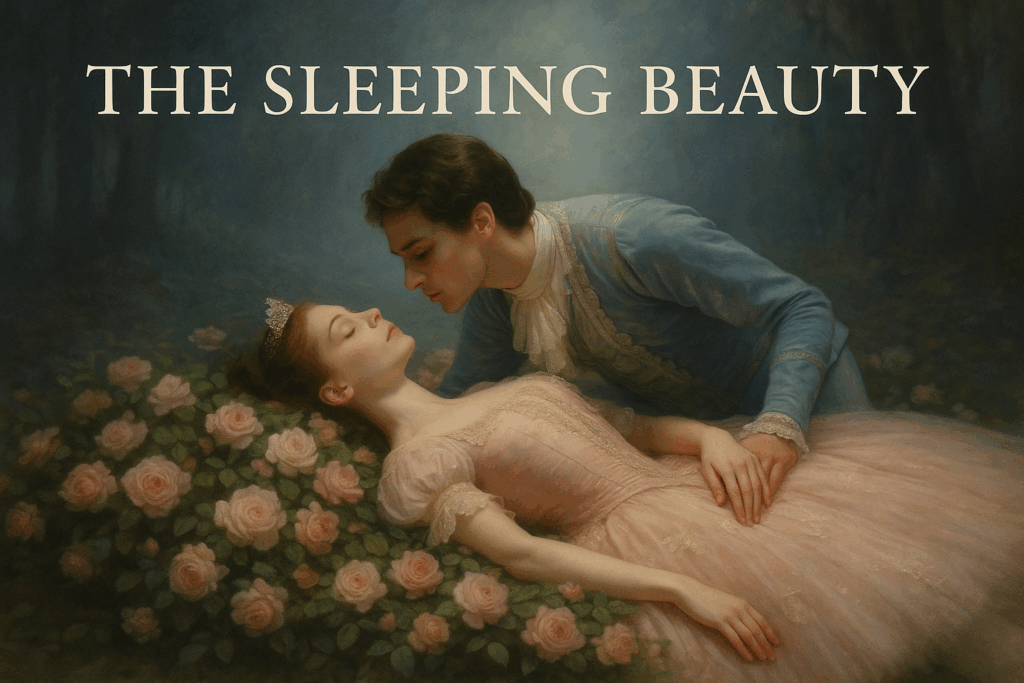
今すぐプライムビデオで観る(公式映像)
《眠れる森の美女》は、チャイコフスキーが作曲し、マリウス・プティパが振付を手がけたクラシック・バレエの代表作です。物語はシャルル・ペローの童話を原作としており、ロマンティックで幻想的な世界観とともに、バレエ芸術の集大成ともいえる舞台美術・音楽・振付が融合しています。
1. 作品概要
- 初演年:1890年1月15日(ユリウス暦)/1月3日(グレゴリオ暦)
- 初演劇場:マリインスキー劇場(ロシア・サンクトペテルブルク)
- 音楽:ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
- 振付:マリウス・プティパ
- 原作:シャルル・ペロー『眠れる森の美女』
- 台本:イワン・フセヴォロジュスキー、マリウス・プティパ
2.時代背景
《眠れる森の美女(The Sleeping Beauty)》が制作された19世紀末のロシアは、まさに帝政ロシア文化が最も華やかで爛熟していた時代でした。その政治的・文化的背景を知ることで、このバレエがなぜこれほど壮麗かつ格式高く作られたのかがよく理解できます。
アレクサンドル3世は強権的な君主として知られ、政治的には保守的でロシア化政策を推進していました。芸術は国家の威信を示す「宮廷文化」として積極的に支援され、特にバレエは皇帝の権威を象徴する存在でした。
また、ロシア上流階級はフランス文化への強い憧れを抱いており、宮廷言語もフランス語でした。マリインスキー劇場支配人であったイワン・フセヴォロシスキーはフランスで絶対王政を築いていったルイ14世の時代の繁栄と調和・威厳をバレエで表現することを発案しました。
原作にルイ14世時代の宮廷人はシャルル・ペローによるフランス童話を選び、舞台もヴェルサイユ風の宮廷がイメージされています。プティパもフランス人で、ロシアで絶大な影響力を持つ振付家。マリウス・プティパによる振付は、ただの踊りではなく、宮廷の格式・美・シンメトリーを強く意識した構成。オーロラ姫のローズ・アダージオなどはその象徴で、「王族にふさわしい品格と統制の美学」が求められています。
このように、《眠れる森の美女》は、帝政ロシアの宮廷文化を表現したような作品として作られ、政治の象徴とし、皇帝にふさわしい格式・美・永遠性をバレエという形で具現化しています。
3. あらすじ
プロローグ+3幕構成。とっても有名な作品なのでご存じの方も多いと思いますが、各幕ごとのストーリーをご紹介しますね
プロローグ:オーロラ姫の誕生と呪い
国王フロレスタンと王妃に待望の娘、オーロラ姫が誕生。宮廷では盛大な洗礼式が開かれ、6人の妖精たちが姫に贈り物(優しさ、気品、美しさ、強さ、など)を捧げます。そこに、招待されなかった悪の妖精カラボスが現れます。カラボスは自信が招待されなかったことに怒り、オーロラ姫に「16歳の誕生日に糸車の針で指を刺して死ぬ」という呪いをかけます。
そのとき、善の妖精リラが現れ、「姫は死ぬのではなく、長い眠りにつき、真実の愛のキスで目覚めるだろう」と予言します。
第1幕:オーロラ姫の誕生日と眠り
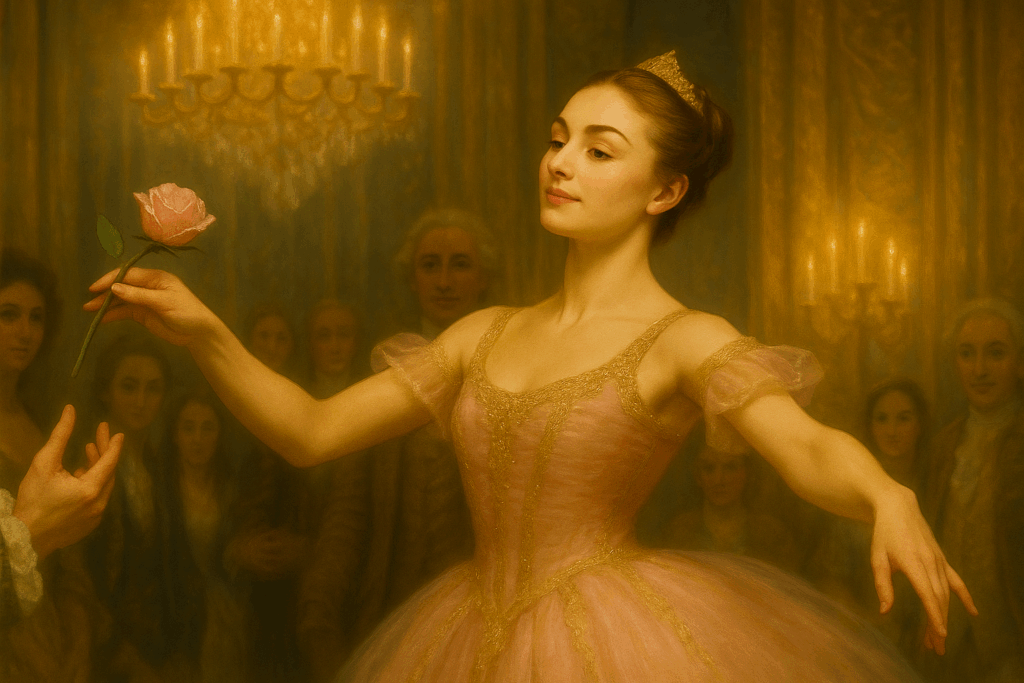
16歳の誕生日、城では王女の成人を祝う華やかな舞踏会が開かれます。各国の王子たちが求婚に訪れ、オーロラ姫はローズ・アダージオで彼らと踊ります。
そこへ、老婆に変装したカラボスが現れ、オーロラ姫に糸車を手渡します。姫はその針で指を刺し、予言通り倒れてしまいます。王と王妃、家臣たちは絶望するが、リラの精が現れ、城全体を眠らせます。そして100年の時が流れていきます・・・。
第2幕:100年後の森、リラの精の導きと目覚め

100年後、王子デジレは森の中で狩りをしています。そこに自身の洗礼の母であるリラの精が現れ、オーロラ姫の幻をみさられます。ひと目で恋に落ちた王子はオーロラ姫にあわせて欲しいとリラの精に懇願します。王子はリラの精に導かれ城にたどり着きます。カラボス一味が見張り眠る城、王子は眠るオーロラ姫を見つけてキスをします。オーロラ姫は目覚め、城全体も100年の眠りから目覚めます。
第3幕:結婚の祝祭
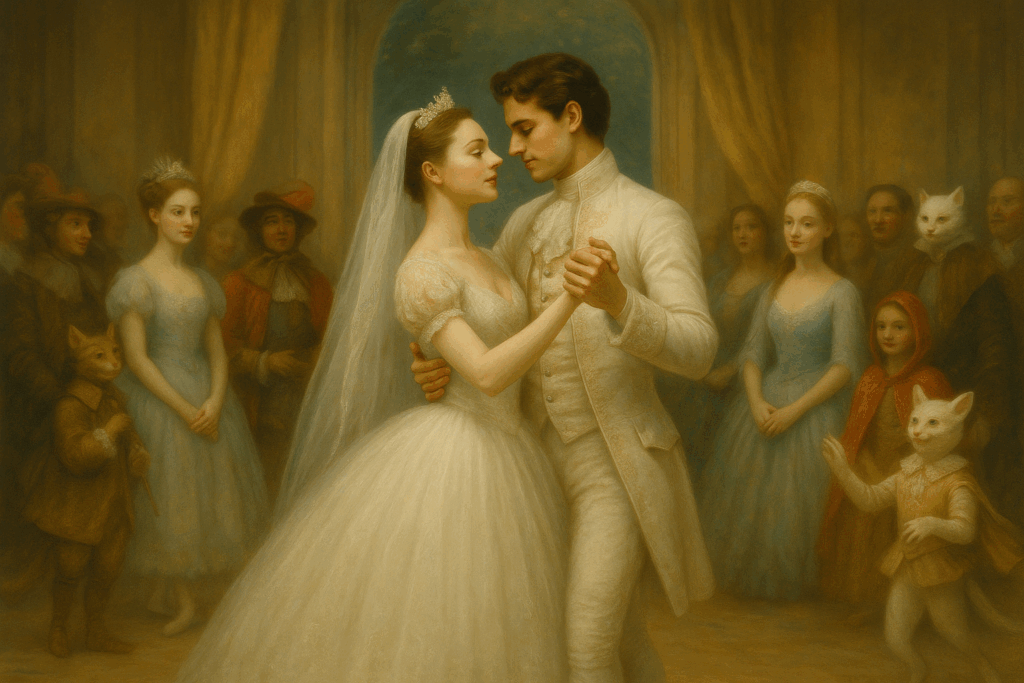
二人は結婚し、城では祝宴が開かれています。祝宴には童話のキャラクター(赤ずきん、長靴をはいた猫、青い鳥など)も登場し、にぎやかで幻想的な踊りが繰り広げられます。2人は祝福され、王国は幸せに包まれるのでした。
4. 各演出版のご紹介
チャイコフスキーの華麗な音楽とともに、格式高い舞台で踊られる《眠れる森の美女》。
その壮麗な構成は時代ごとにさまざまな演出家によって手を加えられ、異なるオーロラ姫が生まれてきました。
今回は、歴史的な代表バージョンを演出年順に紹介し、それぞれの特徴と美しさの違いを見ていきましょう。
| 年 | 演出・振付 | バージョン名 | 主なバレエ団 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | マリウス・プティパ | 原典版(初演) | マリインスキー劇場 | 皇帝文化の象徴。チャイコフスキーと初タッグ。完全クラシカル。 |
| 1921 | ニコライ・セルゲーエフ(伝承) | バレエ・リュス版 | バレエ・リュス | ロンドンでの再創作。英国バレエの礎に。 |
| 1952 | コンスタンチン・セルゲーエフ | キーロフ改訂版 | キーロフ劇場(現マリインスキー) | 原典を基にした保存版。ソ連時代の定番。 |
| 1963 | ユーリー・グリゴローヴィチ | グリゴローヴィチ版 | ボリショイ・バレエ | ドラマティックな構成と英雄的な王子像。ロシア的重量感と迫力のある演出。 |
| 1968 / 1975 | ルドルフ・ヌレエフ | ヌレエフ版 | ウィーン国立歌劇場 → パリ・オペラ座 | 王子の視点を重視。心理劇として構築。音楽構成の忠実な活用。 |
| 1977 | ローランド・プティ | モダン版 | マルセイユ・バレエ団ほか | 現代的で演劇的な再解釈。スタイリッシュで象徴的な演出。 |
| 1981 | ピーター・ライト | ライト版 | バーミンガム・ロイヤル・バレエ | 英国スタイルの王道。物語重視。カラボスに男性配役も。 |
| 1987 | マリシア・ハイデ | シュツットガルト版 | シュツットガルト・バレエ | ドイツ的演劇性。心理描写と表現重視の構成。 |
| 1994(復活) | フレデリック・アシュトン | アシュトン版 | ロイヤル・バレエ | 優美で抒情的。英国バレエのエッセンスが詰まった演出。 |
| 2011 | ナチョ・ドゥアト | ドゥアト版 | ミハイロフスキー劇場 | 詩的かつコンテンポラリー。感情の余韻が美しい。 |
| 2015 | アレクセイ・ラトマンスキー | 復元版(原典再構成) | ABT(アメリカン・バレエ・シアター) | プティパ原典の完全再現を目指す復元的演出。 |
各演出版おすすめDVDのご紹介
5.有名なバリエーションのご紹介
バレエ《眠れる森の美女(The Sleeping Beauty)》には、クラシック・バレエを代表する有名バリエーション(ソロ)が多数登場します。その中でも特に注目される有名バリエーションを、役名・幕構成とともにご紹介します。
| 幕 | 役名・キャラクター | バリエーションの名前・特徴 |
|---|---|---|
| 第1幕 | オーロラ姫 | ローズ・アダージオ後のヴァリエーション 優雅でクラシカル、パ・ド・ブレを多用したソロ。アントルラッセやピケなど技巧も豊か。 |
| 第2幕 | オーロラ姫(幻想) | 夢の中のバリエーション(幻の姫) 柔らかく詩的。王子の幻想に現れる幻想的な存在として踊られる。アームスや呼吸感が重要。 |
| 第3幕 | オーロラ姫 | 結婚のグラン・パ・ド・ドゥのヴァリエーション 華やかで技術的。ピルエット、ジュテ、バランスなど集大成的な内容。 |
| 第3幕 | 青い鳥(男性) | 青い鳥のヴァリエーション 跳躍(アントルシャ・シス)、速いブリゼなど技巧的な見せ場が多く、男性ソロの定番。 |
| 第3幕 | フロリナ王女(女性) | 青い鳥のパ・ド・ドゥ内のヴァリエーション 軽やかで跳ねるようなステップ。ポールドブラが柔らかく羽ばたくような印象。 |
| 第3幕 | 白猫 | 白猫と長靴をはいた猫のパ・ド・キャラクテール内バリエーション コミカルで演技力が問われる。女性はツンとした仕草が魅力。 |
| 第3幕 | 赤ずきん | 赤ずきんと狼のバリエーション(キャラクター) 民話的でおとぎ話らしい演出。演技重視のキャラクターダンス。 |
| プロローグ | 各妖精たち(6人) | 妖精のヴァリエーション(贈り物の精たち) 各精の性格に応じた短いソロ。特にリラの精は舞台全体の雰囲気を決定づける存在。 |
各ヴァリエーションの詳細はこちらから↓

6.幻想と技術が交差する第2幕オーロラソロ、演出ごとのご紹介(動画あり)
バレエ《眠れる森の美女》の中でも、ひときわ幻想的で詩的なシーンが第2幕。個人的に大好きなのが、この2幕のオーロラのソロです。
この森の中でのオーロラ姫は「王子デジレの夢の中の幻想(あるいはリラの精が見せる幻)」として登場します。現実では眠りについたままの彼女が、幻として王子を導くように舞い踊るという設定。そのため、登場から終わりまで全体がどこか浮遊感を持ち、音楽も柔らかく包み込むような調べで進みます。このバリエーションは、各演出版によってニュアンスが大きく異なります。ここではバレエファンならずとも魅了される動画をご紹介。みなさんはどちらがお好みでしょう??
セルゲーエフ版、マリンスキーバレエ団、Alina Somova
個人的に一番好きな振り付け。伏し目がちでフワフワとして幻想的でありながら、品格が漂うバリエーションだと感じます!Somovaさんが美しすぎます! 参考にTheBalletGalleryさんのyoutubeをご紹介させていただきます。
アシュトン版、ロイヤルバレエ団、Marianela Núñez
ドゥアト版、ベルリン国立バレエ団、Iana Salenko
グリゴローヴィチ版、ボリショイバレエ団、Svetlana Zakharova
参考にDanceLine Balletさんのyoutubeをご紹介させていただきます
名ダンサー揃いの動画3連発。演出毎の振りの違いがとっても興味深いですね!アシュトン版は、控えめで眠り続けるしかない、悲しみのようなものが滲み出ているよう。nunezさんの圧倒的な踊りは圧巻!ドゥアト版はあまり観ることがなく珍しいかも。コンテよりの動きも多いですね。salenkoさんの美しいアームスと表現力が魅力的です!そして、zakharova先生による、グリゴローヴィチ版。ダイナミックでザ・王女の気品が漂っていますね!
ヌレエフ版、パリ・オペラ座バレエ、Aurelie Dupont
参考にTomaž Golubさんのyoutubeをご紹介させていただきます。
言わずとしれたデュポン先生!ヌレエフ版は登場のシーンが控えめ、アームスが柔らかく美しくて、丸く包み込むような優しさが感じられる振り付けだなと感じます!
この記事で紹介した映像まとめ
- DVD|チャイコフスキー:バレエ《眠りの森の美女》
- DVD|ボリショイ(ザハロワ/ホールバーグ)
- DVD|英国ロイヤル・バレエ
- Prime Video|ボリショイ(グリゴローヴィチ版)
- Prime Video|英国ロイヤル・バレエ
2025年4月24日(記事UP時の前日)、東京バレエ団ので斎藤友佳里さん振付版の「眠りの森の美女」を観劇してきました。東京バレエ団の2幕はどのバレエ団とも異なり、特に斎藤さんがこだわり抜いた演出。
全幕を通して、オーロラとデジレをつなぐ、洗礼の母である「リラの精」の重要度がさらに増し、この2幕のバリエーションも優しい導きがより深く表現されていました。まだ見たことのない方は、次回公演の機会にぜひこだわりの物語を観てみてくださいね!
生の公演はやはり圧巻!ですが、ご家族気兼ねなく自宅でゆっくりプライムビデオ・DVDでの鑑賞でも。オーロラはもちろん、リラの精、デジレ王子、妖精たち、宝石、フロリナ、青い鳥、どこをとっても圧巻な踊りで、世界観を楽しんでくださいね^^
今すぐバレエの世界に旅立ちたい方は本もおすすめ
舞台を離れても、物語の世界を感じられるのがバレエ漫画や小説の魅力。
「テレプシコーラ」や「ダンス・ダンス・ダンスール」など、
バレエを題材にした名作10選ご紹介しています。期間限定無料作品もありますよ!
→ 2025年版 バレエ漫画&本10選の記事はこちら